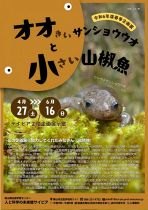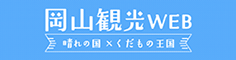観光スポット検索結果 634件
- ジャンル:「歴史・文化」
- 地域:「全エリア」
-
第一合同銀行の倉敷支店として大正11年(1922)に竣工したルネサンス風の建物。大原美術館や有隣荘など、大原家関連の建物の多くに関わった総社市出身の建築家、薬師寺主計が設計しました。鉄筋コンクリ...
-
国産ジーンズの聖地・児島で注目を集める児島ジーンズストリート。「 旧野﨑家住宅 」から野﨑の記念碑までの約400mの通りに地元ジーンズメーカーが軒を連ねています。世界に誇る「ジャパンデニム」のオ...
-
治承・寿永の乱の際、平氏が源氏に勝利した「水島の合戦」の記念碑。水玉ブリッジライン源平大橋(玉島大橋)西側に建てられています。
-
江戸時代後期に大規模な塩田を開き、「塩田王国」を築いた野﨑武左衛門の屋敷。約3,000坪の敷地には、約1,000坪にわたる主屋群と6 棟の土蔵が建ち並び、庭のあちこちに茶室が見られるなど、当時の...
-
大原美術館、倉敷絹織(現(株)クラレ)の創設者 大原孫三郎、大原家代々が暮らした家。国の重要文化財。 邸内は表からは想像できない景色。石畳に連なる倉群、静寂の日本庭園等々、落ち着いた雰囲気の中...
-
下津井は瀬戸内海に面する港町で、江戸時代には、北前船による綿花、ニシン粕の中継取引港として、また、海を隔てた讃岐金毘羅参りをする人々の宿場として大いに繁栄しました。今でも当時の商家やニシン蔵など...