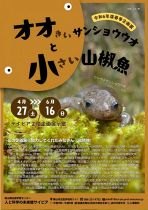プーチン氏5期目 強権な体制に懸念拭えぬ
ウクライナ侵攻を続けるロシアのプーチン大統領が、2030年までの通算5期目に入った。全うすれば首相時代を含め30年にわたり最高権力者の地位にとどまることになり、ソ連時代の独裁者スターリンを抜く。
強権を振りかざし、独裁的な政権運営を一層強める懸念が拭えない。そもそも3月の大統領選は正統性が疑問視された。日本や多くの欧米諸国が先週あった就任式を欠席したのも当然だ。
新たな任期に臨み、プーチン氏は求心力維持のためか、これまで以上に戦時色を強く打ち出している。就任演説では「共に勝利しよう」と国民に結束を呼びかけ、3年目に入った軍事侵攻を完遂する意思を鮮明にした。
ウクライナを支援する西側諸国に対しては「対話は拒否しない」と述べた。ただ、ロシアの国益にかなっていることを前提としており本気度は伝わってこない。
看過できないのは、軍事侵攻での勝利に固執するプーチン氏が侵攻当初から繰り返してきた「核による脅し」が、より具体的になっていることだ。就任式直前には、国内の侵攻拠点で近く戦術核兵器の使用を想定した演習を始めると発表した。欧米への威圧のつもりだろうが極めて危険な振るまいである。
侵攻の長期化を見据え、ロシアの今年の国防予算は昨年の約1・7倍、歳出の約3割にまで膨らんでいる。新政権の閣僚人事では国防相に経済官僚のベロウソフ氏を抜てきし、軍と産業分野の連携を密にしていく構えだ。
こうした動きの背景には、フランスのマクロン大統領が2月、ウクライナへの地上部隊派遣を「排除しない」と表明したり、4月に米議会が、しばらく滞っていた軍事支援の再開を決定したりしたことへの反発があろう。
一方、対ロ経済制裁を科しているのは欧米や日本にとどまる。中国やグローバルサウスと呼ばれる新興・途上国がそれぞれ国益の観点から原油などを買い支え、ロシア経済は揺らいでいないようだ。
プーチン氏は就任後の初外遊として、きょうまで2日間の日程で中国を公式訪問している。外交や安全保障、経済の協力関係を深め、ともに対立する欧米をけん制する狙いがある。習近平国家主席と会談したほか、エネルギー、宇宙開発といった分野の貿易や投資の拡大も図るという。
現下の戦況はウクライナ側が劣勢とされ、加えて西側諸国では「支援疲れ」の広がりも見られる。とはいえ、力による現状変更は断じて許されない。新興・途上国にも粘り強く働きかけ、ロシアに対する結束をいかに強められるかが問われる。
ロシア軍の死傷者の総計は36万人近いと推定される。堅固にみえるプーチン体制だが、権力闘争などが起こる可能性がないとは言えず、混乱への警戒も怠れない。
強権を振りかざし、独裁的な政権運営を一層強める懸念が拭えない。そもそも3月の大統領選は正統性が疑問視された。日本や多くの欧米諸国が先週あった就任式を欠席したのも当然だ。
新たな任期に臨み、プーチン氏は求心力維持のためか、これまで以上に戦時色を強く打ち出している。就任演説では「共に勝利しよう」と国民に結束を呼びかけ、3年目に入った軍事侵攻を完遂する意思を鮮明にした。
ウクライナを支援する西側諸国に対しては「対話は拒否しない」と述べた。ただ、ロシアの国益にかなっていることを前提としており本気度は伝わってこない。
看過できないのは、軍事侵攻での勝利に固執するプーチン氏が侵攻当初から繰り返してきた「核による脅し」が、より具体的になっていることだ。就任式直前には、国内の侵攻拠点で近く戦術核兵器の使用を想定した演習を始めると発表した。欧米への威圧のつもりだろうが極めて危険な振るまいである。
侵攻の長期化を見据え、ロシアの今年の国防予算は昨年の約1・7倍、歳出の約3割にまで膨らんでいる。新政権の閣僚人事では国防相に経済官僚のベロウソフ氏を抜てきし、軍と産業分野の連携を密にしていく構えだ。
こうした動きの背景には、フランスのマクロン大統領が2月、ウクライナへの地上部隊派遣を「排除しない」と表明したり、4月に米議会が、しばらく滞っていた軍事支援の再開を決定したりしたことへの反発があろう。
一方、対ロ経済制裁を科しているのは欧米や日本にとどまる。中国やグローバルサウスと呼ばれる新興・途上国がそれぞれ国益の観点から原油などを買い支え、ロシア経済は揺らいでいないようだ。
プーチン氏は就任後の初外遊として、きょうまで2日間の日程で中国を公式訪問している。外交や安全保障、経済の協力関係を深め、ともに対立する欧米をけん制する狙いがある。習近平国家主席と会談したほか、エネルギー、宇宙開発といった分野の貿易や投資の拡大も図るという。
現下の戦況はウクライナ側が劣勢とされ、加えて西側諸国では「支援疲れ」の広がりも見られる。とはいえ、力による現状変更は断じて許されない。新興・途上国にも粘り強く働きかけ、ロシアに対する結束をいかに強められるかが問われる。
ロシア軍の死傷者の総計は36万人近いと推定される。堅固にみえるプーチン体制だが、権力闘争などが起こる可能性がないとは言えず、混乱への警戒も怠れない。
(2024年05月17日 08時00分 更新)