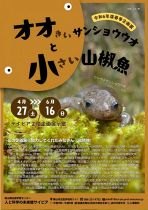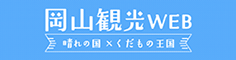わんにゃんメディカ
221年ぶりのせみ時雨
セミは夏の風物詩だが、桜の時季に鳴き始めるものもいる。松林にすむハルゼミだ。先日も旅先の高知県で「ギー、ギー」と機械音のような声を聞いた▼6月初めごろまでが繁殖期で、晩春の季語にもなっている。〈春の〓埴輪(はにわ)作りし祖(おや)のこと〉岩田和代。太古から延々と繰り返されてきた命の営み。セミは恐竜の時代にはもう合唱していたというから恐れ入る▼「せみ時雨」ならぬ「せみ豪雨」を巡る報道で目下にぎわっているのが米国だ。幼虫として地中で13年間暮らすセミと17年間を過ごすセミ、二つの集団が土を破って現れるタイミングが221年ぶりに重なった▼生息域で4月下旬に羽化が始まり、6月にかけて1兆匹以上が大発生するとみられる。鳴き声は電車が通るガード下相当の100デシベルに達する恐れがあるとか。これも次世代を育むための恋の歌と諦めるしかない▼日本のセミと違い、こうした長い周期ごとに出現するタイプのセミは、一斉に成虫になることで繁殖相手を確保したり天敵に捕まる確率を下げたりできる。要は生き残り戦略で、氷河期に適応するために進化したという▼ただ今後は温暖化が作用して早く目覚める個体が増えるとの見方もある。それも自然の摂理か。13年ゼミと17年ゼミの同時発生が次も起こるかは、随分先の子孫の代、2245年まで分からない。
〓は虫ヘンに単の上の点三つが口二つ。読みは「せみ」
〓は虫ヘンに単の上の点三つが口二つ。読みは「せみ」
(2024年05月19日 08時00分 更新)