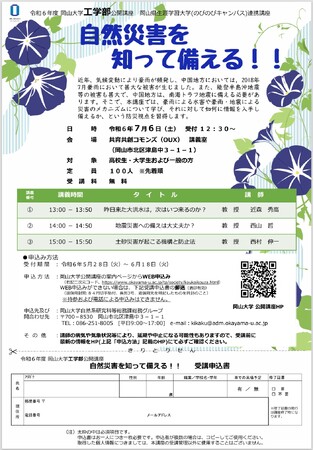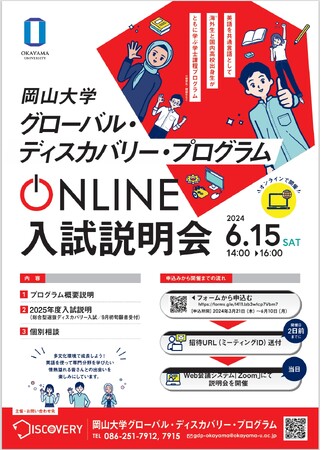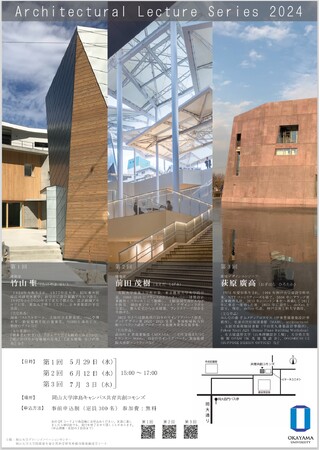戦時中、敵機の襲来をいち早くキャッチするため、全国に防空監視哨が置かれ、地元の青年たちが哨員として24時間で監視に当たっていたという。岡山県が初めて空襲を受けて80年。岡山県内の防空監視哨について岡山市岡山空襲展示室(岡山市北区駅元町)がパネル展示にまとめた。レーダー技術の遅れていた当時の日本で、空の監視は人の目と耳が頼り。離れた敵機の音を聴くための「聴音壕(ごう)」という遺構が岡山市内に残っていると聞き、訪ねてみた。
岡山市北区足守の鍛冶山城跡の一角、竹やぶの中に井戸のようなコンクリート造の大きな筒状の穴が残っていた。外径3・6メートル。コンクリートの厚みは28センチ。こけむして中に木も生えているが、おおむね原形をとどめているようだ。内壁から飛び出す鉄筋は、かつて屋根を支えた柱の名残かもしれない。
意を決して中に入ってみた。すると、近くの鳥のさえずりがふっと消えて静寂に包まれる。単純な構造だが、近くの雑音を遮り、遠くの空から響く音を増幅する効果があるそうだ。不意にゴォーと低い音が近づいてきた。近くの岡山空港を発着する飛行機か。しかし、方位も距離もさっぱり見当がつかない。哨員はレコードの音で機種や高度の違いを聞き分ける訓練をしていたというが、それでも、どれほどの情報が得られたのだろうか。
岡山空襲展示室によると、防空監視哨は1937年制定の防空法、そして41年の防空監視隊令を根拠に各道府県に設置された。岡山県は40年に「岡山県永年防空計画」を策定。付属の防空監視隊一覧表には、県庁内の本部と、おおむね警察署単位の監視哨22カ所の所在地が記されている。
しかし、一覧表に足守はない。岡山空襲展示室がもう1カ所、現地調査した倉敷市玉島黒崎もそう。山陽新聞でも、これまで美作市古町、新庄村、笠岡市北木島などの防空監視哨の跡や証言を取り上げている。岡山県史(1989年)は「県内で20カ所ともいわれるが、正確な数は不明」と記す。同展示室は「最終的には30カ所くらいになっていたと考えられる」とする。
それぞれの防空監視哨で何が行われていたのか。...
岡山市北区足守の鍛冶山城跡の一角、竹やぶの中に井戸のようなコンクリート造の大きな筒状の穴が残っていた。外径3・6メートル。コンクリートの厚みは28センチ。こけむして中に木も生えているが、おおむね原形をとどめているようだ。内壁から飛び出す鉄筋は、かつて屋根を支えた柱の名残かもしれない。
意を決して中に入ってみた。すると、近くの鳥のさえずりがふっと消えて静寂に包まれる。単純な構造だが、近くの雑音を遮り、遠くの空から響く音を増幅する効果があるそうだ。不意にゴォーと低い音が近づいてきた。近くの岡山空港を発着する飛行機か。しかし、方位も距離もさっぱり見当がつかない。哨員はレコードの音で機種や高度の違いを聞き分ける訓練をしていたというが、それでも、どれほどの情報が得られたのだろうか。
岡山空襲展示室によると、防空監視哨は1937年制定の防空法、そして41年の防空監視隊令を根拠に各道府県に設置された。岡山県は40年に「岡山県永年防空計画」を策定。付属の防空監視隊一覧表には、県庁内の本部と、おおむね警察署単位の監視哨22カ所の所在地が記されている。
しかし、一覧表に足守はない。岡山空襲展示室がもう1カ所、現地調査した倉敷市玉島黒崎もそう。山陽新聞でも、これまで美作市古町、新庄村、笠岡市北木島などの防空監視哨の跡や証言を取り上げている。岡山県史(1989年)は「県内で20カ所ともいわれるが、正確な数は不明」と記す。同展示室は「最終的には30カ所くらいになっていたと考えられる」とする。
それぞれの防空監視哨で何が行われていたのか。...
この記事は会員限定です。