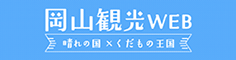寺院
横尾山 静円寺[安楽院][地蔵院](よこおさん じょうえんじ あんらくいん じぞういん)
一山一寺多院制を今に伝える竹久夢二ゆかりの古刹
静円寺は730(天平2)年、行基により創建された。報恩大師に備前四十八カ寺に選ばれた名刹である。境内北側には、大日如来を安置する多宝塔がそびえる。また同寺は、一山一寺多院制の形式を現在に伝えることでも知られる。安楽院の境内には修行大師像が立ち、四国八十八カ所のお砂踏み霊場も整備されている。その隣では、十二支をモチーフにした愛らしい小坊さんたちの像が参拝客を和ませている。地蔵院は、地蔵菩薩立像を本尊として祀る。人形供養祭が有名である。
ご案内
住所/〒701-4214 瀬戸内市邑久町本庄4368
TEL/0869-22-0353(地蔵院)、0869-22-0529(安楽院)
地蔵院ホームページ/https://yokoozanzizouin.jp/
地蔵院インスタグラム/https://www.instagram.com/jizouin_kotetsu/
交通/岡山ブルーライン・邑久ICから車で5分。JR赤穂線・邑久駅から車で10分
宗派/高野山真言宗
ご本尊/千手観音(秘仏)
開山/730(天平2)年
代表的寺宝/備前焼永正銘花瓶(県指定重要文化財)、備前焼永禄銘花瓶(県指定重要文化財) ほか
御朱印/受付8時~17時、各院まで 300円
※不在時は紙朱印を用意
年間行事
毎月17日/縁日法要
1月1日/修正会
5月21日/御影供
8月16日/水祭り施餓鬼法要
12月31日/除夜会
【ここ、知ってる?】
人形供養祭(地蔵院)
地蔵院では、毎年3月の最終日曜日に人形供養祭が行われている。当日は子どもたちが行列をつくり、人形を乗せた花車を静円寺から地蔵院まで引いて歩く。人形に宿った魂の成仏と、子どもの健やかな成長が祈られる光景は、瀬戸内市の春の風物詩として知られる。

静円寺は730(天平2)年、行基により創建された。報恩大師に備前四十八カ寺に選ばれた名刹である。境内北側には、大日如来を安置する多宝塔がそびえる。また同寺は、一山一寺多院制の形式を現在に伝えることでも知られる。安楽院の境内には修行大師像が立ち、四国八十八カ所のお砂踏み霊場も整備されている。その隣では、十二支をモチーフにした愛らしい小坊さんたちの像が参拝客を和ませている。地蔵院は、地蔵菩薩立像を本尊として祀る。人形供養祭が有名である。
ご案内
住所/〒701-4214 瀬戸内市邑久町本庄4368
TEL/0869-22-0353(地蔵院)、0869-22-0529(安楽院)
地蔵院ホームページ/https://yokoozanzizouin.jp/
地蔵院インスタグラム/https://www.instagram.com/jizouin_kotetsu/
交通/岡山ブルーライン・邑久ICから車で5分。JR赤穂線・邑久駅から車で10分
宗派/高野山真言宗
ご本尊/千手観音(秘仏)
開山/730(天平2)年
代表的寺宝/備前焼永正銘花瓶(県指定重要文化財)、備前焼永禄銘花瓶(県指定重要文化財) ほか
御朱印/受付8時~17時、各院まで 300円
※不在時は紙朱印を用意
年間行事
毎月17日/縁日法要
1月1日/修正会
5月21日/御影供
8月16日/水祭り施餓鬼法要
12月31日/除夜会
【ここ、知ってる?】
人形供養祭(地蔵院)
地蔵院では、毎年3月の最終日曜日に人形供養祭が行われている。当日は子どもたちが行列をつくり、人形を乗せた花車を静円寺から地蔵院まで引いて歩く。人形に宿った魂の成仏と、子どもの健やかな成長が祈られる光景は、瀬戸内市の春の風物詩として知られる。

(2023年10月11日 03時30分 更新)






![横尾山 静円寺[安楽院][地蔵院](よこおさん じょうえんじ あんらくいん じぞういん)](http://static.sanyonews.jp/image/article/786x590/9/d/d/8/9dd82040bd281f70ad0426904468b386_2.jpg)


![横尾山 静円寺[安楽院][地蔵院](よこおさん じょうえんじ あんらくいん じぞういん)](http://static.sanyonews.jp/image/article/786x590/9/d/d/8/9dd82040bd281f70ad0426904468b386_5.jpg)